- ~環境で育つ~ 2024.04.08
-
―この世のすべての生命は与えられた環境の中で生きていきます―
いきなり堅苦しい話で恐縮ですが、幼稚園教育要領や保育所保育指針に謳われている幼児の育ちは「環境・人間関係・言葉・表現・健康」の5つの領域に分けられています。幼稚園教諭免許や保育士資格を持つ人は学生時代に大学や短大等で必ずこのことを学ぶわけですが、実は「人間関係」も「言葉」も「表現」も「健康」もすべては「環境」の中に存在しており、環境とは人を含め、あらゆる動植物の育ちに大きくかかわる大切なものだと私は常々考えています。
たとえば、花を育てる時に必要なのは空気や水や太陽という環境ですが、この環境が十分に整っていないとすればどうでしょう。十分な光や水が与えられなければ、つまり花の育ちに必要な環境が与えられなければ、花を咲かせるどころか、その前に萎れたり枯れてしまうことになるでしょう。
これを幼児の育ちに当てはめるとするならば、家庭における環境や幼稚園・保育園における環境が何より大切だということになります。この世のすべての生命、とりわけ乳幼児の育ちというのが家庭や園での物的環境や人的環境に大きく左右されるとするならば、花が咲くのに必要な要素 ― 空気や水や太陽に相当する環境を子供の良好な発達・成長のために整えてあげなければなりません。
昨今、乳幼児への虐待、またはスマホやタブレット任せの育児、あるいは園における不適切保育等が社会問題として取り上げられることが多くなりました。このことをふまえ、我々、乳幼児教育に携わる者は今一度、生命の育みというのは与えられた環境によって良くも悪くもなるということをしっかり認識して日々の保育に当たらなければなりません。
当園の保育が新たにご縁を頂いた新園児を含めすべての子供達の育ちに必要不可欠な存在になるべく精一杯務めさせていただく所存ですので今年度もよろしくお願いいたします。
下のボタンをクリックしてください。
- ~希望の光~ 2024.03.01
-
希望とは車のキーみたいなもの
失くしたと思っても探せばすぐ見つかる
人が生きていく上で大切なものは?と問われたとき ―「愛」であるとか「感謝」であるとか ― その答えは人それぞれなのでしょうが、今回は生きていく上で必要な「希望」についてお話いたします。
言うまでもなく「希望」の反対語は「絶望」で、その言葉が示すとおり望みが消えてしまった時に抱く気持ちを表していますが、その状態とは「光」のない真っ暗闇の世界とも言えるでしょう。そして人は大なり小なりこのような心の状態に陥った経験が必ずあると思います。さて ― そんな時、あなたならどうしますか?
この答えもまた「人それぞれ」と言えばそこまでですが、ネガティブな心の状態をリセットする何かが必要であることは間違いありません。先日映画を観ていた時、ある役者のこんなセリフに共感を覚えたのでご紹介します。
もっとも強い希望とは絶望の中から生まれる
人は「まさか!」という厳しい現実に直面したり、怒りや悲しみの感情に至ったとき「もうダメだ」とすべてを投げ出して諦めてしまいがちです。心の中でキラキラ輝いていた光が消えて暗闇の世界でもがき苦しむ。しかし、どんな暗闇の中でも、生きている限り希望の光は必ず見つけることができるはずです。いや、むしろ絶望を味わうからこそ、そこから新たな希望が芽生える。だとすれば、本当の意味での絶望とは、光が二度と戻らないと思ってしまう心の闇のことを言うのでしょう。
春は希望あふれる季節です。閉め切った心の窓を開けてみれば、まぶしい春の光とあたたかな風が、心の中をリフレッシュしてくれるはずです。そしてまた新しい一歩を踏み出してみようではありませんか。
下のボタンをクリックしてください。
- ~かけがえのないこと~ 2024.02.01
-
失われた時 はじめて気づく 当たり前のありがたさ
元日に起こった能登半島地震で被災された多くの方々、突然奪われてしまった多くの尊い命。そして今もなお、余談ならぬ状況下で不自由な避難生活を強いられている方々が多くいらっしゃることを耳目にする度に暗澹たる思いがこみ上げてきます。
誰しもが感じるはずの新年の喜びに浸る間もなく誰しもが予想だにしなかった大震災。そして一昨年まで長く続いたコロナの禍中おいても同様に私がつくづく感じたことがあります。それは、当たり前のように過ごす日々―何の変哲もない毎日―ありきたりで平凡な毎日―それこそが、我々にとっていちばん大切で掛け替えのないことである。つまり何をおいても失いたくない―奪われたくないものは、何か特別な日ではなく、ルーティーンのように繰り返される判で付いたような何気ない日常の日々だということです。
仏教の教えのひとつに「諸行無常」という言葉があります。「平家物語」の冒頭にも次のように引用されているので、高校の授業で習った記憶がある方もいらっしゃると思います。
祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり
祇園精舎の鐘の音には,この世のすべての現象は絶えず変化していくものだという響きがある。という意味ですが、この「諸行無常」の字が示す通り、この世にあるものはすべて変化しとどまることがない―つまり常であることはない―だから無常である。洒落ではありませんが「無常」であることがある意味「無情」なのが世の中なのかも知れません。
ならばせめて、朝起きて夜寝るまでの間の様々な生活の場面を「最近変化がなくて全然つまんないわ~」と嘆くのではなく「毎日変わらないことが何よりもありがたくて掛け替えのない」と思えるように、今そこにある暮らしに感謝する心を持ちたいものです。
下のボタンをクリックしてください。
- ~新年の思い~ 2024.01.10
-
何となく 今年はよい事 あるごとし 元日の朝 晴れて風無し
石川啄木
新年あけましておめでとうございます。これから始まる一年最初の朝に晴れ渡った青い空を眺めながら、清々しい空気を思いっきり吸い込むと、何となく今年はよい年になりそうな予感がする。そんな気持ちを詠ったこの句が私は大好きで、毎年元旦に思い出しては「何事も大難は小難に、小難は無難に過ごせますように。そしてほんのちっぽけな幸せでいい。それをひとつでも多く感じることができる一年になりますように―」と願うばかりです。
しかし、春夏秋冬の一年を過ごす間には、いいことばかりではなく、冷たい雨や逆風に晒される日もあるでしょう。そんな時にはどうすればいいか?私なりの答えは二つあります。
ひとつ目は「食」です。美味しい物や自分の好きな物、普段はあまり口にできない高級な物でもいいし、ケーキやお菓子類でも構いません。逆境の中でも必死に頑張っている自分自身にご褒美をあげましょう。あえて言いますが、この際、体重を気にするのはやめましょう。ダイエットのことなどはきれいさっぱり忘れて、とにかく自分の大好きな食べ物をぱくぱく口に運んでみてください。
そうすれば「あら?!まあ~不思議!!」さっきまで重たく沈んでいた気持ちが徐々に軽くなってくるのがわかります。ぺちゃんこになった心が少しずつ膨らんでいくのがわかります。そこで二つ目の「笑」です。自分の好きなお笑い番組やコメディ映画を観て腹の底から笑いましょう。面白いから笑うのか?笑うから面白いのか?どちらにしても「笑う門には福来る」なので自然に笑える環境に身を置くことが大事です。ちなみに私のお勧めは吉本新喜劇です(笑)。あと、かわいい小動物に触れたり眺めたりするのもいいでしょう。きっとあなたの心を癒してくれ、いつの間にかニッコリと微笑んでいる自分に気づくことができます。
如何でしょうか。「食」と「笑」は偉大なり!このふたつは人を元気にする源です。いっぱい食べていっぱい笑って、今年が皆様方にとってすばらしい一年になりますように―。
下のボタンをクリックしてください。
- ~時の流れに身を任せ~ 2023.12.18
-
川の流れは よどむことなく うたかたの時 押し流してゆく
昨日は昨日 明日は明日 再び戻る今日はない
あんなに暑かった夏は、まるで存在さえしなかったようにすっかり鳴りを潜めて、今では目に映るものや肌で感じるものすべてが冬以外の何ものでもないという師走を迎えたある夜、ふたりのおっさんが屋台でしんみりとお酒を飲んでおりました。
A「うーっさむ‥」「今夜はごっつう寒いで‥」
B「ほんま‥かなわんわ」
「ちょっと前までは“暑い暑い”言うとったのに」
A「そやな、今では二言目には“寒い寒い”って、ついつい言うてまうなあ‥」
B「ほんまやで。わてはもう“あつい”って言うこと‥ないと思うわ‥。って、
熱っ!熱っ!あつーっ!なんや!このおでん‥熱すぎやでえーっ!」
A「言うとるやん‥“あつい”って。ほんま、せっかちなやっちゃ‥」
せっかちだろうが、のんきだろうが、時というのはいつも変わることなく、たとえ「いったいいつまで続くの?」と感じていた時間さえも、確実に流れて行く。だからこそ今日一日を有意義に過ごすということも大切ですが、人生にはそれが出来ない日も必ずあります。つまり好調な時もあればスランプの時だってある。しかし、どんな時間さえも止まることなく未来へ流れて行くのなら、辛いことや悲しいことがあっても、あたふたせずに、たまには時の流れに身を任せてみてもいいのかも知れません。師走の夜、冷たい風に吹かれながら、過ぎ去りし酷暑の夏に思いをはせて、ふとそんなことを思いました。
下のボタンをクリックしてください。
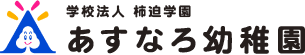
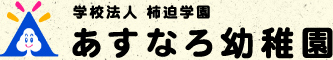


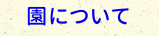
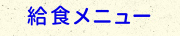
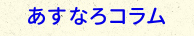
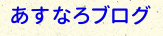
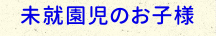
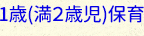
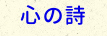
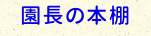


 閉じる
閉じる
 1
1