- ~心の力~ 2020.11.01
-
今年はコロナの影響で多くの飲食店が廃業になり、西日本一の歓楽街、中州でも人通りはまばらで、ネオンの灯りが一層寂しさを演出しているような気がします。そのような状況下、芸能人も多く訪れる中州を代表する高級クラブ「ロイヤルボックス」の藤堂ママがある取材の中でこんなことを言っていました。「負けると思えば負ける、勝つと思わないと絶対勝てない」
実はこのママはジャンケンがものすごく強いことでも有名で、なぜそんなに強いのかを聞くと、ジャンケンをする前に「必ず勝つ!」という自己暗示をかけて勝負に臨むから勝つ。勝負前に「ひょっとしたら負けるかも・・・」なんて思い描くと大体が負けるそうです。
その昔、話題になったマーフィーの法則をご存知でしょうか。マーフィー氏は「あなたの人生はあなたの心に思い描いたとおりになる」と主張して有名になりました。仮に「人生なんて思い通りにならない」と思っている人がいるとしたら、その人の思い通りにならないという思いが、思い通りになっている。ですから、どんな状況でも悲観的にならず思い通りになると信じて行動することが大事だというのです。例えばシンデレラは継母にいじめられながらも夢をあきらめませんでした。そしてついに奇跡を呼び起こしたのです。
これは古い童話の話ですが、心には我々の想像をはるかに超えたパワーがあると私は思います。そしてその力はプラスにもマイナスにもはたらきます。「必ずうまくいく」と強く思えばよい結果が生れるのです。ただし、心の中にほんの少しでも心配や不安を抱えるとやはり結果もそのとおりになるようです。穏やかな心は穏やかな人を引き寄せ、喜びの心には笑顔が返ってきます。逆に怒りや憎しみの心はそのとおりの結果を引き起こします。心を夢や希望で満タンにして有意義な毎日を送ることが出来ればと願い、ジャンケンが弱い私はジャンケンに勝つ心の訓練をしたいものです。
下のボタンをクリックしてください。
- ~適応力~ 2020.10.01
-
あんなに暑かった今年の夏もお彼岸を過ぎた頃からすっかり秋めいてきました。季節はめぐるといいますが、朝晩の気温や澄み切った青空、いつの間にか早くなった日没時間などいたるところに秋の訪れを感じることができます。
しかし、なかなか終わりが見えないのがコロナですね。WITHコロナの言葉の通り、私たちは否応なしにコロナとの共存を強いられてしまっている現状に変化はありません。マスク、消毒、そしてディスタンス。新しい生活様式などと謳われプライベートのみならず皆さんの仕事の考え方やスタイルも随分と変わってきたのではないでしょうか。
最初は不便さや違和感を覚えたことも慣れてくれば「これって結構いいかも」などと思えたりすることがあるならば、これこそが人間の適応力の凄さと言えるでしょう。まさに「人間万事塞翁が馬」で、生きていれば好ましくないことも必ず起こりますが、その状況から逃げたり拒否したりせずに、真っ向からしっかりと受け止めて覚悟を決めれば、今まで出来なかったことも出来るようになる。私はそう信じています。
さらに誤解を恐れず言うならば、人のしあわせは、目の前のすべてを受け入れた時から始まるのではないでしょうか。日常生活の中で起こるさまざまな出来事を他人事ではなく自分の事として受け入れてみれば案外、肚が座って迷いがなくなる。そうなれば必ず「あの手この手」というアイデアや発想が生まれ、新しい世界が見えてくる。現実と向き合い、それにしっかり適応できるかどうか、しあわせはそこから始まり、その可否に人の真価が問われている気がします。
何でも自由に手に入るのがしあわせではなく、汗水流したり知恵を絞ったりアイデアや工夫を強いられる現実に生きているからこそ人は生きがいややりがいを感じる。今を生きる自分に思い上がることなく、どんな事が起きてもすべてを受け入れて適応する力が、これからも我々に求められることでしょう。
下のボタンをクリックしてください。
- ~夏の終わりに思うこと~ 2020.09.01
-
長い梅雨が終わった途端、ここ近年続いている猛烈な夏の暑さに覆われた日本各地、中には体温を超える気温を記録した地域などもあり、日本の夏はすでに、むかし社会で習った温帯という気候区分を変えるべきではないかと思うくらいの暑さでした。そしてこの暑さは、まだまだ続くことが予想され、コロナのみならず、暑さに対する策をも講じながらの9月になりそうです。
そのような中、園庭で水かけ遊びを楽しんでいる子供達の笑顔や歓声に接すると、夏の水遊びは子供にとってなくてはならないアイテムなんだなぁ~と改めて実感いたしました。今年はコロナで至る所の海水浴やプールが開かれなかったので、家庭用のミニプールがよく売れたという話を聞きましたが、夏=子供=水遊び、という関係からしたら、それも当然の事なのでしょう。
そして、もうひとつ。夏と言えば花火ですね。こちらもやはり密を避けるために全国の名だたる花火大会が中止となりましたが、花火師たちは黙っていませんでした。サプライズ花火と銘打ってコロナの終焉を願って打ち上げられた光と音のスペシャルショーに心癒された方も多かったのではないでしょうか。
以前にも述べましたが、すべての事象は、始まれば必ず終わります。真夏の夜空に打ち上がる花火は刹那的に終わり、暑い暑いと言っていた夏とて、やがては終わり秋を迎えます。終わってほしくないものもあれば、早く終わってほしいものだってある。
まさに、「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり」、はたまた「ゆく川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」と同様に、世の中のすべてのものに不変のものはない。ということです。ならば、コロナとて、いつかは必ず終焉する。そのことを信じて、いつかはきっと、という明日への希望を胸に、立ち止まらずに前を向いて共に歩いて行きましょう。
下のボタンをクリックしてください。
- ~ほんの小さなしあわせ~ 2020.08.01
-
春一番に吹き飛ばされることもなく、梅雨の雨に洗い流されることもなく、私たちの心の中にずっと沈み込んでいる鉛のような暗澹たる気持ちを8月の燦々と輝く夏の太陽が跡形もなく溶解してくれることを願ってやみません。
なぜこのような事態になってしまったのか、今さら嘆いても仕方のないことですし、考えても結論は見出せず、誰も答えを教えてはくれません。ただ言えることは、このまま悶々と重たい鉛を引きずりながら日々を過ごしていくには、いずれ限界があるということです。
そのような中、無邪気に遊ぶ子供たちの姿を見ていると、やはり心が和みます。見ているだけで幸せな気分になれたり思わず笑みがこぼれたりするのは、子供が持っている魔法の力と思わずにいられません。
私たちは日常生活の中で、当たり前だと感じることには、あまり目を向けなくなり、平凡な毎日に飽き飽きして、何か新たな刺激を求めてしまう傾向があります。「当たり前じゃつまらない。もっと何かが欲しい。もっともっと満たされたい。」
童話「青い鳥」は、主人公のチルチルとミチルが鳥籠を持ってしあわせの青い鳥探しの旅に出るという話ですが、結局は鳥を連れて帰ることは出来ませんでした。なぜなら本当のしあわせとは、過去や未来、はたまた、どこか遠くにあるものではなく、今いるあなたのそばにしかないからです。
そうです。今、あなたのそばにいる子供、そして家族。共に泣き笑いの生活を送る平凡な毎日そのものが、本当のしあわせなのです。「しあわせはいつも自分の心が決める」詩人の相田みつをさんの言葉のとおり、日常の当たり前の中についつい埋もれてしまいそうな、ほんの小さなしあわせこそが本当のしあわせと思えれば、心の鉛も軽くなることでしょう。
下のボタンをクリックしてください。
- ~ホタルの光~ 2020.07.01
-
緊急事態宣言の解除からおよそ1ヶ月余りが過ぎ、季節が梅雨から初夏へ移り変わる7月を迎えました。新型コロナがなければ、今頃は、オリンピックの話題で世界や日本のあちらこちらで盛り上がっていたことでしょう。そのことを思えば、とても残念でなりません。
しかし、すべてが終わったわけではなく、人々の努力で少しずつ少しずつ今まで当たり前だった日々の生活が戻りつつあるのも事実です。
園生活においても、衛生面に最大の注意を払いながら、さまざまな活動を徐々に再開する中、子供達の屈託のない笑い声が戻ってきたような気がします。そして、今、個人的に思うことは、やはり一日も早くマスクをしないで保育が出来れば‥。ということです。
なぜなら、人と人とが接する中において、言葉はなくても表情で相手に思いが伝わることがあるように、子供にとって保育者の優しい表情は、時に言葉以上の力を発揮し、子供が安心して心の扉を開いてくれる表現のひとつです。
それほど大切な保育者の表情をマスクが覆い隠してしまい、何となくもどかしさを感じてしまいます。ましてやこれからの季節は、暑さと息苦しさで、マスクをしたままの保育はかなり苦痛を伴うのですが、これも園における新しい生活様式として受け入れなければならないことなのでしょう。
そんな中、先日、ホタルの特集をした雑誌を読む機会があり、夜の川面に舞う無数のホタルの光に癒され元気をもらいました。もし、人の心にも闇を照らす光を灯すことが出来れば、言われなき偏見や差別もきっとなくなる。ひょっとしたら人はマスクをすることで優しい光まで閉ざしてしまうのではないのか。そんなことをホタルが語っているような気がしました。
下のボタンをクリックしてください。
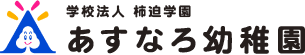
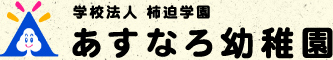


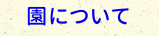
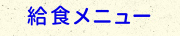
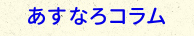
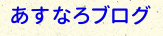
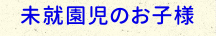
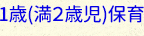
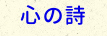
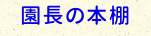


 閉じる
閉じる
 2
2 いいね!
いいね!