- ~大丈夫の力~ 2023.02.01
-
あなたが痛みに耐えたり、苦しんだり、悲しんでいる時に、誰かからそっとやさしく「だいじょうぶ?」と声をかけられると何故だかほんの一瞬だけでも気持ちが楽になったことがありませんか。
あなたが二進も三進もいかない八方ふさがりの大ピンチに陥っている時に、誰かから力強く「だいじょうぶよ!きっと、だいじょうぶ!」と声をかけられると何故だかほんの一瞬だけでも「ひょっとしたら大丈夫かも‥」と思えたりしたことがありませんか。
耐え難く忍び難い苦痛であったり、眠れないほどの不安や心配事、はたまた逃げ場のない窮地に立たされて、どこをどう見ても決して“大丈夫”なんかじゃない時に、誰かからの「だいじょうぶ?」や「だいじょうぶ!」という言葉にほんの一瞬だけでも救われたことがあるとするならば、それは「だいじょうぶ」という言葉が持つ不思議な力のおかげではないかと私は思います。
~~~~~~~~~~~~~~
あるミュージカルの主役の座をかけたオーディションを目前に控えた稽古で、私はかなり焦っていた。歌詞を間違えたりセリフが飛んでしまったり‥。「こんなに私、ダメだったっけ‥」と落ち込んでいる時、母親が突然倒れたという知らせが入り、急いで病院に駆けつけると、意識を取り戻した母がベッドに横たわっていた。「だいじょうぶ?お母さん」「ありがとう。心配かけちゃったけど、あなたの言葉で少し元気になったわ。それより明後日は大事なオーディションでしょ?頑張らなきゃ」「それが‥あんまり調子よくないから、たぶんダメかな‥」「何言ってるの。きっと大丈夫よ」「でも‥歌詞間違えるし‥」「大丈夫!」「セリフ飛んじゃうし‥」「大丈夫!」「ぜんぜん自信ないし‥」「大丈夫!」「もう、どこが大丈夫なのよーっ!」「大丈夫と思えば大丈夫よ。人は生きている限り大丈夫なの。大丈夫じゃないのは死んだ時だけ。だからどんな時でも生きていれば大丈夫!と思いなさい。大丈夫は生きる力、明日への希望なのよ」母はこの言葉を残した数日後、帰らぬ人となった。そして今、私は念願だった夢の舞台に立っている。母の「大丈夫は生きる力」という言葉を胸に刻んで。
下のボタンをクリックしてください。
- ~無のこころ~ 2023.01.01
-
年末に先祖代々のお墓に行き掃除をしてお参りする。そして年が明けると神社に行き初詣で手を合わる。とかく人というのは「こうありたい」とか「こうしたい」や「こうなってほしい」などの願いごとが尽きないわけでして、事あるごとに神社仏閣にお参りに行く。古来よりそんな習慣が我々には根付いているようで‥。
年が明けたある日、たいそうご利益があると名高い神社に初老の夫婦が初詣にやってきました。そして神前に立ちお賽銭を入れようとした時、おもむろに妻が呟きます。「さて、何をお願いしようかしら‥あなたはどうなさる?」
すると夫はこう答えました。「無だよ。いつも「無のこころ」でいられるようにお祈りするんだ。人は生きているといろんな感情が湧いてくる。喜びや楽しさの感情がプラスなら悲しみや怒りがマイナスの感情だ。この感情が曲者で、人はついついプラス感情に振り回されて色んなことを求め過ぎてしまう。そしてそれがうまくいかないと怒りや悲しみなどのマイナス感情に染まってしまう。つまりプラスとマイナスの往来を繰り返して一喜一憂してきたのが今までの私達だったんじゃないかな。もっとも若い頃はそれも二度とない人生を味わう上で必要なことだったが、お互いもういい年だ。これからは感情に左右されないプラマイゼロのニュートラルな気持ちで人生を送れるように「無のこころ」でお祈りするんだ」
夫の話を聞いた妻はコクリと頷き、ふたり一緒に「無のこころ」でお祈りを済ませ清々しい気持ちで神社を後にしました。
夫「ところでだな‥ニュートラルな人生とは、ゴルフでいうパープレイって奴でな」
妻「はあ?何のことですか?」
夫「いや‥今、使ってるパターがイマイチなんで‥そろそろ新しいのが欲しい‥かな‥」
妻「あなた、ちょっといいかしら?」
夫「な、なんだ?」
妻「この、罰当たり!」
下のボタンをクリックしてください。
- ~年の瀬のある夜に~ 2022.12.21
-
令和4年も残すところあとわずかというある日、ふたりの男が一年を振り返りながらしんみりとお酒を飲んでいました。
A「やっぱり、あれやな‥」
「なんやかんや言うたって今年もコロナ‥コロナ‥またコロナの一年やったな‥」
B「ほんまやな‥」
「ところで、あれ外国じゃコビット19(COVID-19)って言うとるけど‥」
「いつの間に増えたんやろ?」
A「いつの間にって‥そりゃ、あっという間に世界中に広がってもうたがな」
「なに言うてんねん‥今さら‥」
B「いや‥最初は7人やったやろ?」
A「はあ?」
B「いや、最初は7人でハイホーハイホーって歌いよったやんか?楽しそうに」
「それがいつの間にか19人って‥えらいこっちゃでえ」
A「なんの話やねん‥」
B「白雪姫の小人が19人全員でハイホーハイホー歌とったら、やかましくてかなわんがな」
「せめて7人までやで‥小人は。19人はなんぼ考えても多すぎや」
A「お前の頭がハイホーじゃ!」
なかなか収まらないコロナ禍の中、大変不謹慎な笑い話かも知れませんが、毎日のニュースで感染者数を確認しては園生活や園行事をどうするか‥。そのことばかりをずっと考えながら過ごしてきた一年でしたので、せめて今年最後のコラムぐらいは笑い話で終わりたいな‥という気持ちをどうかご容赦ください。そして、これから迎えるクリスマスから年末年始にかけての日々が皆様方に笑顔と喜びをたくさんもたらし、来年が今年以上に素晴らしい年になる事を職員一同願っています。今年も大変お世話になりありがとうございました。皆様のご厚情に感謝申し上げ筆をおきます。
下のボタンをクリックしてください。
- ~「やり方」より「あり方」~ 2022.12.01
-
人は何かに取り組もうとする時、「どうやったらうまくいくか?」と考えるものです。それはそれでとても大切なことです。なぜなら「やり方」が悪かったために失敗することがたくさんあるからです。だから人は失敗しないためのいわゆる~How to~を知識や技術として手に入れようと学ぶのです。
しかし、知識や技術を学び「やり方」だけがうまくなればいいのか?! といえば、そうではありません。
何かに取り組もうとする時「やり方」よりもっと大切なものがあります。それは「あり方」です。つまり「どんな心構えでそれを行うのか?」「どんな思いで取り組むのか?」「何のためにやるのか?」そういったことをしっかり心に描くことが大切です。
しかし、人は失敗しないための「やり方」ばかり気にして、いつの間にか「何のために」という目的や「何を目指すのか」という目標を見失ってしまうことがあります。確かに日常の保育や行事を行う時、どうしたらうまくいくかという「やり方」を大いに学んで実践することで身につくことはたくさんあります。
しかし、どんなに素晴らしい知識や技術を学んで実践しても「あり方」~For what~をしっかり持っていないと道を誤ることだってあります。誤解を恐れず言うなら仕事は資格や技術だけでするものではなく「心」でするものなのです。
「技術数年、精神一生」という言葉は、技術を身につけることは数年で可能ですが、仕事に対する心の「あり方」が常にぶれない人間性を磨くには一生かけても難しいという意味です。「やり方」も大事ですが、仕事に対する真っすぐな気持ちを忘れずにいれば、常に「良い心のあり方」で仕事ができ素晴らしい成果を上げることができるでしょう。「やり方」より「あり方」是非、心にとめておきたいものです。
下のボタンをクリックしてください。
- ~こどもは宝~ 2022.11.01
-
幼い子がすやすや眠る姿やよちよち歩く姿、はじけるような笑顔を見ていると「子どもって何てかわいいんだろう」と思いますし、そんな幼子を見ていきなり「コンチクショー!」と怒りだす人はおそらくいないでしょう。これがまさに子どもの魅力であり、こどもは宝と言われる所以です。
瓜食(は)めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ
銀(しろかね)も金(くがね)も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも
これは奈良時代の歌人、山上憶良の有名な歌です。ご存知の方も多いと思いますが、彼は子どもへの情愛を込めた歌をたくさん作っています。
最初の歌は、旅先で出された食べ物をいただいてる時に、その食べ物が大好きな子どものことをついつい思い出してしまったという心情を歌っています。そして次の歌は金銀などのどんな宝よりわが子に勝る宝はないという意味です。これらの歌にあるように古来よりいつの時代も変わらず“こどもは宝”だったのです。さらにこれを私なりに言わせれば、子どもは宝物がいっぱい詰まった“宝箱”だと思います。
子どもは宝箱、そしてその宝箱のカギを開けるのは私たちです。宝箱のカギを開けるとそこにはキラキラ輝く宝の原石がいっぱい詰まっています。そうです!それが子ども達の可能性の原石です。磨けば磨くほどキラキラと輝く原石です。
日々の保育の中で体を動かしたり声を出したり家庭ではできないいろんな体験を通して磨かれていく。そして今までできなかったことが出来るようになる。この子にこんな力が!あの子も、その子も、どの子も持っている潜在能力を開花させるのが我々の役目だと言えます。あすなろ幼稚園はそこにこだわり続ける園でありたいと考えています。
下のボタンをクリックしてください。
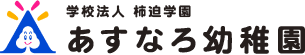
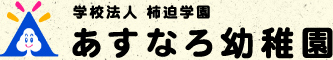


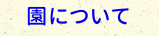
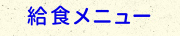
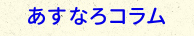
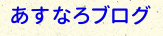
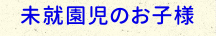
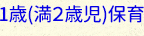
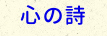
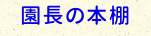


 閉じる
閉じる
 2
2 いいね!
いいね!