- ~涙の力~ 2023.11.01
-
悲しみの涙を流している人を見た時、もらい泣きするのは悲しみの底の深さを知っているから。そして、その悲しみを奇跡的に乗り越えて歓喜のあまり流す涙を見た時に、再びもらい泣きするのは、悲しみの底で希望の光に巡り会えた喜びに心が震え感動するから。
むかし、こんな歌詞の歌がありました。「人は悲しみが多いほど 人にやさしくできる」
そのわけは以下の通りと私は解釈しています。
「人は涙をたくさん流すことで 心が洗われ 瞳が澄んでくる
だから 悲しんでいる人の傷ついた心が 痛いほど よく見えるのだ
そして その澄んだ瞳は いつの日か
悲しみの底で わずかに灯る 希望の光を 見つける力になるだろう」
― 私は幼かった頃、よく泣いた
悲しかったり 悔しかったり 寂しかったり
その度に めそめそ泣いた 父はそんな私を見て
よく叱ったものだ 「泣くんじゃない 男は泣いちゃダメだ」
でも・・母はちがった 泣いている私の頭を やさしくなでながら
「思いっきり泣きなさい 涙は心を ピカピカにしてくれるから
おめめと心が スッキリきれいになるまで いっぱい いっぱい 泣きなさい」
そう言って 私と一緒に 母も泣いてくれた ―
悲しみや喜びで心震える時に流す涙が、心を豊かにして感性を磨いてくれるとするならば、涙の力ほど偉大なものはありません。赤ちゃんから幼児期の子供がよく泣くのは、きっと「涙が心を育ててくれているのだ」と思えれば、泣いている子供への見方、接し方も変わってくるのかも知れませんね。
下のボタンをクリックしてください。
- ~心の持ち方~ 2023.10.01
-
暦は深まりゆく秋を感じる10月ですが、毎年9月の敬老の日を迎える頃になると、あらためて思うことがあります。それは「何だかんだ言っても―ご高齢者の皆さんって、すっごくお元気!」ということです。その証拠に、先日、ある新聞でこんな驚きのポエムを見つけましたので小欄にてご紹介いたします。
今日はあちこちきれいにした 一人住まいも20年 わたしは100歳を超えた
台所も 一つ一つの引き出しも きれいにした とても気持ちよい
100歳の人生も 反省という手入れをして きれいに生きよう
「反省」というタイトルが付けられたこのポエムの作者は東京都在住、102歳の男性です。まさにあっぱれ!というか、最近、体がすっかり固くなり、座ったり立ち上がる時に「よっこらしょ」とか「「アイタタタぁ~」など、ついつい口に出してしまう私は、このポエムを読んで大いに反省したところでございます。(苦笑)
そんなある日のこと、「乙女会」という名の食事会に招待された小生。それは名前のとおり、わたくし以外の4名全員が“うら若き乙女”‥ではなく‥こともあろうに乙女とは程遠いイカツイこわおもてのおっさんが揃いも揃って、みんな9月生まれのおとめ座だという‥何とも“オーマイガッ!”な食事会です。
メンバーは83歳を筆頭に、ほとんどが後期高齢者の大先輩方なので60歳手前の小生などは“ひよっこ”でございます。ですからピヨピヨと鳴(泣)きながら先輩方のお相手をする訳ですが、おとめ座とは名ばかりのイカツイ強者揃いですから―。なかなか帰りません、というか帰してくれません。結局三次会まで宴は続き、ようやく帰宅した小生が這うように寝床に就いた時、サミュエル・ウルマンの詩の一節が頭に浮かんできました。「青春とは人生のある期間ではなく心の持ち方をいう」~先輩方、どうぞ、いつまでも青春でいてください~
下のボタンをクリックしてください。
- ~愛されキャラ~ 2023.09.01
-
巷でよく言われる「愛されキャラ」、その特徴とは?と問われれば、まあ、いろいろあると思いますが、私なりに身の回りを見渡して「あ~あ、いたいた!」と思い当たる人物の共通する決定的な特徴をひとつ申し述べさせていただきましょう。
それは、天然ということです。養殖ではなく間違いなく天然記念物。それほど貴重な存在です。何ゆえ貴重かと申しますと、思考や発想、それに伴う言動がその他多数とは少々異なり、おもしろ過ぎるからで、そんな人がその場にいただけで雰囲気は和みます。
具体的なエピソードとして、こんなことがありました。夏休み期間中、当番で出勤したA先生。製作の作業中、指をケガしてしまい病院に行き戻ってきました。事前にお金のことを何も言わなかった私は、すぐさま治療費をどうしたかが気になり、先生「お金はどうした?」と尋ねました。すると彼女曰く――「財布から出しました!」――。
A先生‥。私はね‥お金を財布から出したかどうかを知りたかったわけじゃないのよ。でも、間違ってないよ。お金は普通、財布から出すもんね。はいはい。その通りでござんすよ。
はたまた、こんなこともありました。朝掃除の時間にB先生の口の周りの黄色い付着物を発見したC先生が尋ねます。「B先生‥ひょっとして朝ごはん、タマゴ食べました?」するとB先生、「えっ!?何でわかるとっ??すごーい!超能力やーん」いやいやいやB先生、そうきますか?ついでに申しますと、Tシャツにもタマゴのシミがついてますけど‥。
最後に電話。私宛にかかってきた電話を取り次いだD先生。かけてきた相手は某取引業者のモトカドさんという方。すかさずD先生は私に向かって大声で「えんちょうせんせーい!」「モトカノさんから電話でーす!」その場にいた先生たちの動きが止まったことは言うまでもありません。ちなみに‥モトカドさんは男性です。さてさて、まだまだ残暑厳しい折ですが、このような「愛されキャラ」たちに囲まれ癒されながら日々過ごしております。
下のボタンをクリックしてください。
- ~絵になる人生~ 2023.07.18
-
昭和を代表する歌手―島倉千代子さんの歌にあるように、人生はいろいろです。例えて言うなら、生まれた時は真っ白だったキャンバスに年齢を重ねるごとに、あるいは、いろんな経験をすることにより、いろんな色やカタチを描いていく。そしてやがて人生の終焉を迎える時、真っ白だったキャンバスには、その人にしか描けなかった世界にたった一枚だけのオリジナルの絵が完成するというわけです。
生きるということは、毎年ひとつずつ必ず歳を取るということですが、そのプロセスにおいて人は、外見はもちろんのこと中身もどんどん変化していきます。その良し悪しは別として、うれしかったり、楽しかったり、悲しかったり、辛かったり‥という経験を通して描かれる色やカタチが次から次へと上書きされ続けていきます。
うれしい時や楽しい時の色は黄色やオレンジ、はたまたピンクでしょうか。逆に悲しみのどん底に落ちた時の色は黒でしょうか。グレーでしょうか。ブルーな気分なんて言葉もありますから、青だったりするかもですね。
世界的な名画と言われるさまざまな作品、例えば…ピカソやゴッホの絵を間近でよく見ると、あらゆる色がちりばめられていることに気づきます。そこには楽しい気分の色だけではなく、悲しくなるようなダークな色もある。まるで作者の悲喜こもごもの人生が、いろんな色に染まってキャンバスの中で息づいているようです。したがって絶望の淵にあるような暗い色も、全体を俯瞰して見れば、その絵にはなくてはならない重要な色だったりする。
つまり、絵画というのは、喜びも悲しみもひっくるめて生きている我々の人生そのもの。絶えず入れ替わる悲喜を日々経験すればするほど、その人なりの味わい深い人生となる。そしていよいよ今際の一筆を描いた時、自分だけの名画が完成するのです。人生は一枚の絵画。ぜひ皆様もたくさんの色やカタチをキャンバスに描き続けて、世界にたった一枚、あなただけのオリジナル絵画の完成を目指して日々お過ごしください。
下のボタンをクリックしてください。
- ~教育は共育~ 2023.07.01
-
教育とはその字が示すとおり、教えて育つものですね。そして育つ対象は、教えてもらう人と言うことになりますが、育つべき存在はそれだけではないと私は常々思っています。
例えば授業などで先生が生徒に教える内容をすべての生徒が即座に理解してくれればいいでしょうが、中にはいくら教えても理解してくれない生徒だっているはずです。そんな時、先生はこう思い悩むことでしょう。「何度も説明しているのに‥どうして、わかってくれないんだ‥」
そこで求められるのが“教え方”なのです。教え方が上手な人とそうでない人がいるとするならば、その差は何か?それは教える側に立つ人が常に“教えながら学ぼうとする気持ち”があるかないか、ではないでしょうか。
教師は生徒にいろんなことを教えますが、実はいろんなことを生徒から教わることだってきっとある。教える過程においてうまくいかない時には、あの手がダメならこの手がある、この手がダメなら他の手はないか‥などなど試行錯誤を繰り返し、何とかしようと努力することで“教え方”の腕を上げていきます。それがいわゆる経験なのです。
経験とはただやみくもに年数を重ねることではなく、上述のような努力の繰り返しの中で培われていくものだと私は思います。
教育とは教わる側も育ち、同時に教える側も育つ。両者が共に育つ共育である。学校はもちろん家庭においても同じことが言えるのではないでしょうか。子育てとは親育ちと言われるように、どんなに大変なことがあっても寄り添う気持ちを大切に日々過ごしていけばいつの日か必ずお互いの信頼の深まり共に成長することができる。学校教育も家庭教育も一方通行ではなく双方の対面通行で学び合うことがその真髄と言えるでしょう。
下のボタンをクリックしてください。
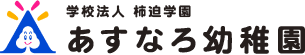
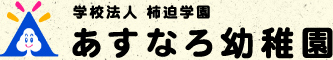


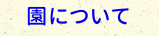
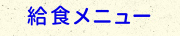
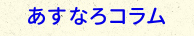
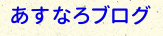
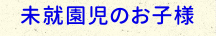
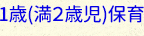
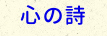
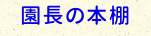


 閉じる
閉じる
 いいね!
いいね! 3
3