- ~忘れちまった悲しみに~ 2017.07.01
-
「昨日の食事をすぐに思い出せますか?」
「何を取りに行ったか忘れてしまうことありますか?」
「名前がどうしても出てこない・・・という経験がありますか?」
私のある知人が、物忘れのひどくなった母親の付き添いで病院に行き診察前の受付で、上記のような問診アンケートを渡され、思わず苦笑したそうです。「この内容って‥ほとんど私にも当てはまっているじゃない‥」
昔の歌に「ちょっと前なら覚えちゃいるが・・」というフレーズありましたが、誰にでも度忘れと言いましょうか、突然、記憶が消えて「あれっ何だっけ?えーっと‥あれよ!あれっ!」と地団駄を踏むような経験があると思います。度忘れ、物忘れ、勘違い等々‥。記憶に関して人は、案外もろいものですが、そのことをつい忘れちまって、深い悲しみに打ちひしがれるという私の私淑する作家のこんなエピソードを紹介します。
あるホテルでの講演会を終えて、預けたカバンとコートを受け取るべくクロークへ。しかし「お待たせしました」と手渡されたのは、カバンだけだったので、すかさず「コートは?」と尋ねたところ「お客様からお預かりしたものはカバンだけですが‥」という返事。
あるはずのものがない、とあっさり言われては、後には引けず「あるはずだ!」「いえ、ございません」「いや!絶対預けた」「何かのお間違えでは‥」の繰り返し。そこで、この作家の脳裏に一瞬、イヤな予感が浮かび、自宅に電話をかけました。「もしもし、そこいらにコートは、ないよな?」しかし、たまたま玄関先にいたのか、家人からの返事は即答で「ありますよ」でした。
あるはずのものがないのは困りますが、ないはずのものがあるのはもっと困ります。この事態を収拾すべく「すまん‥家にあった」と詫びた時の敗北感と言ったら、忘れちまった悲しみに今日も風さえ吹き過ぎる、だったそうです。
下のボタンをクリックしてください。
- ~クワバラ クワバラ~ 2017.05.29
-
それはあまりにも突然でした。バケツをひっくり返したような雨がパレード隊を襲い、逃げ惑う人々を狙い撃ちする雹は、まるで戦場の砲撃のようでした。
博多のGWと言えば、街を彩るどんたく祭り。多くの観光客も訪れて、その賑わいは全国的にも有名ですね。しかし、博多の人は知っています。どんたくには雨がつきものだということを・・。
時期的な問題なのかどうかはわかりませんが、兎にも角にも、私が少年のころから、どんたくは雨という記憶が脳裏にしっかりと刻まれています。
しかし、今年の5月の3日、4日の天気予報は晴れマークだったので、誰しもが、今年のどんたくは雨が降らない、と思ったことでしょう。ところがどっこい、飛んでも八分歩いて十分、その予想はもろくも崩れ、午後からだんだん雲行きが怪しくなり、冒頭の嵐のような雨に見舞われました。
私の知り合いもパレードの順番待ちをしている最中、まさかの雨に、傘もなく、近くに雨宿りする場所もなく、衣装はもちろん下着までもが全部ずぶ濡れに。ご本人いわく「逃げ場を失った濡れネズミのようだった」そうです。(クワバラクワバラ)
当然パレードはそこから中止。知り合い御一行は、ずぶ濡れのためタクシーにも乗れず、やけのやんぱちの捨て鉢状態で、とぼとぼバス停まで歩き、バスの車内では、ぽたぽた水を滴らせ、他の乗客の憐れむ視線をじっと耐えながら帰宅したそうです。来年のパレードは「晴れても雨カッパ持参」これが今回の惨事で生まれた教訓らしいです。
さて、クワバラクワバラとは、古来より雷除けのおまじないとして唱えられたそうですが、季節はまもなく梅雨に入ります。皆様も突然の雨やその他の災いがわが身に降りかかることがないようにクワバラクワバラを折にふれて唱えられることをお勧めします。ちなみに「つるかめつるかめ」というおまじないもセットに使用すると効果はさらにテキメンです。
下のボタンをクリックしてください。
- ~5月の風~ 2017.05.01
-
春の嵐も過ぎ去り、五月の風に、陽だまりの新緑が眩しく揺れています。そして勇壮に泳ぐ鯉のぼり。どこまでも続く青い空に浮かぶ雲たちは、吹く風に行き先を尋ねながらゆっくりと流れていきます。
園庭に吹く風もやわらかく、子ども達にひとり、またひとりとタッチしながら、固くなった心と体をやさしくほぐし、涙で濡れた頬を乾かしてくれます。子ども達にとって、あすなろ幼稚園の先生達は、そんな五月の風のような存在でいたいと願っています。
そして、野原に寝そべり、空に浮かぶたくさんの雲を見ていると、あらためてひとつとして同じ形がないことに気づきます。そんな雲のように、一人ひとり違った様子や表情を見せてくれる子ども達。晴れた日の雲はふわふわ真っ白でも雨の日にはどんより曇ってしまいます。しかし、晴れても曇っても雨が降っても子どもの心にしっかりと寄り添いながら、心の花を開いていく。あすなろ幼稚園はその花が満開に咲く野原のような存在でいたいと願っています。
「言うは易し行うは難し」という言葉もあるように、何をするにしても、口で言うのは簡単でそれを実行するのは大変難しいわけですが、「念ずれば花ひらく」という言葉もあります。そして我が家にある松岡修造氏のカレンダーにはこんな言葉もありました。「できるできないではなくやるかやらないかだ」大事なことは思いを強く心に念じてコツコツと一歩ずつ前に進むこと。
まもなくゴールデンウィークです。幼稚園がお休みでも外に出ると、五月の風が優しく子ども達を抱きしめてくれることでしょう。その風はきっと幼稚園の先生達です。そして、ハウステンボスなどの行楽地で見られる満開の花で溢れる花園は幼稚園そのものです。そう言える幼稚園、そう言える先生でありたいと願いながら、爽やかな五月の風を胸いっぱいに吸い込んで、これからも流れる雲を追いかけて行きます。
下のボタンをクリックしてください。
- ~ヒューマンタッチ~ 2017.04.10
-
人間が行う仕事の約半分が機械に奪われる。あすなろコラムの1月号でも紹介しましたオックスフォ―ド大学でAI(人工知能)などの研究を行うマイケル・A・オズボーン准教授の論文は世界に衝撃を与えました。
さらに、あるコメンテーターによると、人工知能の急激な発達によって現在、日常で行われている仕事がロボットに代行されることになり、近い将来には、10人中9人は今とは違う仕事をしているだろう、ということです。
また、今年、小学校に入る全世界の子どもたちの65%が、将来、いまはまだない仕事につく。とも言われています。スピルバーグの映画「バック・トゥ・ザ・フユーチャー」が封切されたのは、私が学生時代でしたが、当時はまだ非現実的でピンとこなかった覚えがあります。しかし、今となっては映画に登場した技術のほとんどが実現可能になったようです。
ちなみに、この映画、先日、死去されたロック界のレジェンド、チャック・ベリー氏も登場します。主人公のマーティーが演奏するギターの影響を受けて、あの名曲「ジョニー・B・グット」が生まれたことを彷彿させるシーンが懐かしく思い出されます。
閑話休題。しかし、いくらコンピューターやロボットの技術革新が進んでも変わらない仕事もあります。それは創造力を活かしたクリエイティブな領域、そして何と言っても、スキンシップやヒューマンタッチが必要な子育てです。
どんなに時代が変わってもロボットにはない生身の人間の肌の温もりが伝わる保育は、人間にしかできないのです。AI社会においても人間にしかできない尊い仕事、それが子育てなのです。ハイタッチよりニューマンタッチ、人間にしかできない役目・役割を、我々は今、担っているという思いを胸に、新年度の第一歩を踏み出したいと思います。
下のボタンをクリックしてください。
- ~春はそこまで~ 2017.03.01
-
国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。
これは、ご存知の通り、川端康成の小説「雪国」の有名なフレーズです。先般、上越新幹線「ときMAX」で東京から新潟へ行く機会がありました。東京の空は雲一つなく、車窓から差し込む日差しが、とても眩しいほどの快晴でした。あっという間に、上野駅、大宮駅を過ぎ、群馬県の高崎駅に停車した際も、見渡す限りの青空で、穏やかな天候に変わりはなく、車内で読書に耽っていた私も、ついウトウトと眠ってしまいました。
気が付くと「間もなく越後湯沢駅に到着します」という車内アナウンス。窓の外に目を向けるとちょうど長いトンネルに差し掛かったらしく真っ暗の窓が鏡となり静かな車内を映し出していました。その静かな車内にどよめきが起こったのは、列車がトンネルを抜けた瞬間でした。

高崎駅を出てわずか30分足らずで、この景色の変化。まさに小説の世界そのものでした。そしてこの時、私は思いました。「雪は白でよかったなぁ~」「もし、雪が黒だったら雪国の人は大変だろうなぁ・・」

「汚れっちまった悲しみに 今日も小雪の降りかかる」という詩がありますが、苦しみも悲しみも心に降る純白の雪が覆い尽くしてくれる。そして、やがて訪れる春を心待ちにする。春になれば、雪解け水が嫌なことを洗い流してくれる。そう、春はもう、すぐそこまで。
下のボタンをクリックしてください。
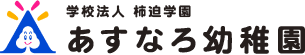
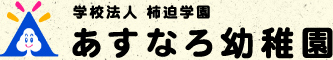


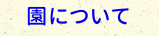
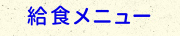
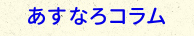
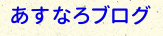
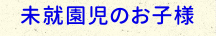
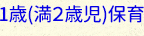
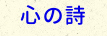
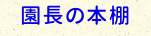


 閉じる
閉じる
 いいね!
いいね!