- ~人生は出会いのドラマ~ 2018.01.10
-
作家、井伏鱒二の「さよならだけが人生だ」という言葉は有名ですが、人生において別れがあるということは、その数だけの出会いがあったということです。新しい年に、さて今年はどんな年になるんだろう、と思いを巡らせている方も多いと思いますが、人生の一コマ一コマは人や出来事との出会いによってそれぞれのドラマが展開されていく。ですから私は「さよなら」ではなく「出会いこそが人生だ」と言いたいのです。
我々の日々の生活は、昨日と全く同じ今日はなく、望むと望まざるに拘わらず、さまざまな人や出来事との出会いを繰り返しながら時が過ぎていきます。しかもその出会いは十人十色で、その人なりの出会いが織りなす人生のドラマが物語のページを埋めていく。これが人は自分の生涯を、世界にたった一冊しかない本にすることができると言われる所以です。
平成30年。第何章目かは それぞれでしょうが、今年も皆様の人生ドラマがスタートしました。主役はあなた自身です。「出会いこそが人生」。つらい事や苦しいこともきっとあるでしょうが、楽しいことやすばらしい出会いもきっとある。「苦楽は生涯の道ずれ」ですから、どんな時も希望を失うことなく、今年のページに自分なりの物語を描いてほしいものです。
さて、この「あすなろコラム」ですが、毎月園だよりに掲載し続けて10数年。来年の今ごろには200回の節目を迎えることとなります。内容の善し悪しは別といたしましても、これを書き続けることは私の大切なライフワークです。いつの日か、今までのバックナンバーをまとめたエッセイ集を上梓できたらと思っています。しかし、日々の業務に追われている毎日‥。さて、いつの日になるのやら‥。
下のボタンをクリックしてください。
- ~ラジオな夜~ 2017.12.20
-
先般、平成31年4月30日の今上天皇の生前退位をもって、平成時代の幕が閉じられることが発表されました。戦後の高度経済成長に生まれ、思春期から青年時代を昭和という時代で過ごした私には、昭和が終わる時ほどの身につまされるような寂寥感はありませんが、やっぱりひとつの時代が終わるというのは何となく寂しいものですね。
何かにつけて昭和と比較された平成ですが、30年もの間に我々の生活にさまざまな変化をもたらせました。中でもいちばんの変革は、アナログ時代からデジタル時代へということでしょう。そしてIT革命によりコンピューターが職場や家庭で欠くことのできない存在になった。そんな時代が平成です。
善し悪しは別として、時代が変われば、今まで必要とされてきたものが要らなくなり、姿を消すことになります。例えば、今、家電店でラジカセなる存在は、絶滅危惧家電に指定されています。(すでに、ラジカセって何‥?っていう人もいるのでしょうか‥。)今どきカセットテープを使う人などほとんどいませんもんね。
私の青春時代は音楽などを録音するのは100%カセットテープでしたし、ラジカセを通じてラジオ放送も深夜を中心によく聴いていました。当然、お気に入りの人気番組もたくさんありましたし、今でもそのことを思い出すと、懐かしさとちょっぴりセンチなほろ苦さが胸に込み上げてきます。
そんな折、先日、出張先のホテルでNHKラジオの「ラジオ深夜便」という番組を聴く機会がありました。スピーカーから聴こえるパーソナリティの声や音楽はシンプルでありながら心に優しくもしっかりと響くまさに昭和のラジオがそのまま現代にも生きていました。
平成という時代も生きてきた私にとって、平成を悪く言うつもりは毛頭ありませんが、何でも手軽さや便利さを追求したがゆえに、深さよりも、より広く浅くなり過ぎたような気がします。最近のテレビを見ると旅やグルメ、動物またはクイズものばかり。どれも同じに見えて仕方ありません。
お笑いタレントにしても、オシャレさはあるものの何となく軽い。昭和時代のハードなストレートパンチ的な強烈なキャラクター性に欠ける。万人にウケたいがために、リスクを避けてしまうから個性が消える。そんなことをあれこれ思いめぐらせながら、深夜放送のパーソナリティの囁きと仄かな部屋の明かりに包まれながらゆっくりとゆっくりと眠りにつきました。ラジオな夜、皆様も、たまにはいかがでしょうか。昭和を知っている人には特におすすめです。
下のボタンをクリックしてください。
- ~そしてまたひとつ~ 2017.12.01
-
毎年、年の瀬に思うことは、過ぎてしまえば一年っていうのはあっという間であるということです。あっという間に一年が過ぎるのではなく、過ぎてしまえばあっという間ということですが、この違いがわかる人は、ネスカフェ・ゴールドブレンドを飲んでいる人だと思います。
さて、仕事にしてもプライベートにしても、人はやりたいことよりも、やらなきゃならないことの方が多いものです。特に年末には、やらなきゃならないことがいっぱいあり過ぎて、何から手をつけたらいいのやら訳がわからなくなる。そこへさらに追い打ちをかけるようにやらなきゃならないことが次から次へと押し寄せてくる。
そんな時はどうするか。答えはかんたんです。まずは、目の前のことをひとつずつこなしていく。やらなきゃならないことがたくさんあるからといって一挙に片づけることはとても困難です。ましてや、あれもあるこれもあると先々のことばかり考えていると気分が滅入ってしまいます。ですから、まずは目の前のやるべきことをしっかりやることが肝要です。
ひとつ済めばまたひとつ。次から次へとやるべきことを片づけていく。そうすると手帳を真っ黒に埋めつくした膨大な所用も、時が過ぎるごとに、自ずと片づけられていきます。そのようにして日々過ごしていると、物事が片付くまではすごく長く感じていたことが、片付いてしまえばあっという間だった。つまり、過ぎるまでは長く、過ぎてしまえば意外と短かった。と思えるのです。
やりたいこともやらなきゃならないことも含め、時の流れの中で、わき目も振らず、取り組んでいく。そして、ふっとカレンダーを見ればもう12月。今年もやっぱり過ぎてしまえば、あっという間の一年だった。きっと来年の年の瀬も同じ思いが頭に浮かぶことでしょう。
下のボタンをクリックしてください。
- ~非認知能力~ 2017.11.01
-
「夏休みの宿題を終わりがけになってしかやらない子どもは、大人になって禁煙できず、ダイエットできず、貯金も少ない」先般、こんな耳の痛い話を聞きました。
来年の4月から学習指導要領や幼稚園教育要領、保育所保育指針等の改訂が行われますが、その中に「非認知能力」という言葉が頻繁に出てきます。つまりこれからの学習には、認知される能力(認知能力)以外の能力をも高めることが強く求められていくということです。
認知能力とは、学力テストや偏差値、はたまた100メートル走のタイムなど数字に表れる能力、いわゆる数値化された能力のことを言います。一方、非認知能力とは数字では表されにくい能力ということになります。さてその能力とは一体、何でしょうか。
冒頭の話は子どものみならず大人にとっても大変耳が痛い話ではありますが、たとえば計画性や実行力、自制心や忍耐力と言った能力は、はっきりと数値化されにくい能力と言えるでしょう。つまり、私なりの解釈を言わせてもらえば、認知能力とは学力や身体能力、非認知能力とは人間性や社会性と思うのです。
卵と鶏の話がありますが、学習における理想は、認知能力と非認知能力の良好なバランスにより保たれる。ならば、小中学校や幼稚園、保育園において学習する機会には、そのことをしっかり踏まえましょう。ということです。
かつてのゆとり教育により学力が低下したために、学力を伸ばすプログラムとして、各自治体では土曜授業などの取り組みも始まりました。加えて、来年度の指導要領や教育要領の改訂により、各教育機関の集団生活において、あいさつや掃除、人や物に対する思いやりや感謝の心を育てるプログラムにより、子ども達の社会性や人間性が高まるよう期待しますし、自らも教育者として実践できればと思います。
下のボタンをクリックしてください。
- ~理想の保育者~ 2017.10.01
-
「あなたはなぜ、保育者になりたいと思ったのですか?」 この問いかけに対して、「私は子どもが大好きだからです。」と答える人が多いと思います。もちろんこれはとても良いことだと思います。 なぜなら、もし、子どもが嫌いな人がこの仕事に就いているとすれば、保護者は子どもを安心してあずけることはできないでしょうし、何より本人にとって、とても不幸なことです。
しかし、少々意地悪な質問ですが「子どもが好きなだけで保育者になれると思いますか?」こう問われればいかがでしょうか。答えは賛否両論かもしれませんが、私は「子どもが好き」ということは保育者にとって欠くことができない要素ですし、まずは、その気持ちがなければ保育の仕事は務まらないのですが、それだけでは不十分だと思います。
では、何が必要か?それは、子どもに好かれるという事です。何故なら「子どもが好き」であれば必ず「子どもから好かれる」という訳ではないからです。「子どもが好き」ということはもともと本人がそう思っていることですから、格別の努力の必要はありません。しかし、「子どもから好かれる」には努力が必要です。そしてこの知恵を絞ったり工夫を凝らす努力をすることこそが保育者に求められられることです。
保育現場で、先生が子ども達に好かれているかどうかは、日常のふとした時に垣間見られます。子どもに好かれている先生のまわりには、いつも子どもの笑顔が溢れています。まるで、その先生に吸い寄せられるように集まってくる子ども達。言うまでもなく「子どもに好かれる」ということは子どもにおもねることではなく、誤解を恐れず言えば、叱られることもあるけど先生が大好きということです。まさに子どもと先生の信頼関係と言えますが「信頼」とは、人間関係を良好にする一丁目一番地です。子どもから好かれる保育者は、いつもそこに住んでいる子どもが大好きな人で、それこそが私が思う理想の保育者です。
下のボタンをクリックしてください。
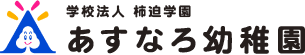
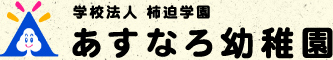


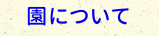
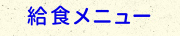
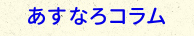
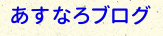
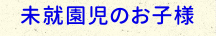
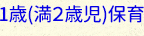
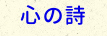
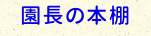


 閉じる
閉じる
 いいね!
いいね!