- 「東京2」
- 2022.04.23
-
東京2~冷やし中華とチャーハン~
工業高校を卒業した僕は東京の下町風情あふれる小さな町工場に就職が決まりひとり暮らしを始めた。―小さな町工場―と言っても、そこは精密加工品の分野では名が知れた会社で、あらゆる顧客オーダーに対応する技術を持っているので大手にはできない特殊なオーダーを受けた時は朝早くアパートを出たら夜は帰って寝るだけの生活が続き食事はもっぱら外食になる。そんな仕事帰りに僕がよく立ち寄るのは近所にあるちっぽけな大衆食堂だ。店主のおばちゃんがひとりで切り盛りしているためメニューの数は少ないけどボリュームたっぷりの定食類がおいしく、おまけに夜遅くまで営業しているのでとてもありがたい。
五月晴れの時期を過ぎ梅雨入りも目前に迫った蒸し暑い六月のある日、その日も遅くに仕事を終えた僕は汗だくのまま店に行き閉店間際で客がいない店内のカウンターに座った。顔を上げて見慣れたメニューをながめるものの暑さのためかどれもあまりピンとこない。しばらく悩んでいると「食べたいもの、言ってみて。作ってあげるよ」とカウンターの中から声をかけられた。「えっ、いいんですか?」「いいよ、私に作れるものならね。お兄さんよく来てくれるし、顔覚えちゃったよ。だから常連さんだけの裏メニューってことで」「じゃあ‥冷やし中華、出来ますか?」
「う、うまい!」しゃきしゃきのキュウリとのど越しのよいひんやりした麺。ちょっぴり甘酸っぱい醤油ダレが火照った胃袋を刺激し食べるほどに食欲がわき一気に完食した。「ごちそうさまでした。おいしかったです」「そう、よかった。ところでお兄さんは、いくつ?」と訊かれ年齢を言うと「へえ~っ、そっか。若いのに感心だね、夜遅くまで働いて。私にも遠方で暮らす息子がひとりいてね、あなたを見てるとまるで“息子が目の前に座ってる”ように思えて嬉しくなるの。しかも同い年だしね。で、出身は?」「九州の博多です」「えっ⁈ 博多‥なの?」と言いながらおばちゃんは僕のつなぎ服の胸元に縫われた苗字に目をやり突然顔色を変えた。「あなたのフルネーム‥って、ひょっとして‥?」「はい。そうです、けど‥」
――ま、まさか‥。―― まさか、こんなことが起こるなんて‥。
翌日の朝、目覚めると、あの後どうやって店を閉めて帰って寝たのかまったく覚えていない。まるで治りかけた傷のかさぶたを思いっきり剝がされたような痛みを伴う衝撃的な再会‥。そんな自分の運命におびえつつ、あの日のことが脳裏によみがえっては罪の意識に押しつぶされそうになる。
結婚して嫁いだ先が博多だった。東京で生まれ育った私にとってはまるで未知の世界。独特の言葉や甘過ぎる味付けに馴染めなかった私は一癖も二癖もある姑から“できない嫁”として容赦ない口撃を受ける。やがて長男が生まれると今度は育児にもあれこれダメ出しされ、居た堪れなくなった私は気晴らしにと長男を連れて外出した。バスに乗ってすやすや眠る息子を眺めていると前席から嫁姑らしき親子の楽しげな会話が聞こえてくる。やがてお姑さんは私の存在に気づき話しかけてきた。よく喋りよく笑うお姑さん、そして私と同じく東京から嫁いで来たお嫁さん、すごく仲が良さそうだった。その姿を見ていると自分の境遇がすごくみじめに思えて涙が止まらなかった。それでも、それからおよそ一年、かわいい我が子のためにずっと我慢の日々を過ごしてきたが、ある日発覚した旦那の浮気の原因がさも私にあるようなあり得ない姑の言葉に呆然とする。「あんたのせいじゃなかと?」
――私のせいではない、はずだけど。ある意味‥私のせいかも知れない。――
知らない土地に馴染めなかったこと、姑に気に入られなかったこと、初めての育児に追われ旦那に構えなかったこと、そして‥気付けば毎日泣いてばかりだったこと。あの日、バスで出会ったお姑さんの言葉が思い出される。「家族の中の誰かが、家族の中の誰かを泣かすような家族はしあわせじゃなか」もしそうならば‥。
――私のしあわせはきっとここにはない。――
その後まもなく離婚が決まり、ようやく息子とふたりっきりになれる、はずだったが姑から「子供はぜったい渡さんけんね!この子ひとりぐらいこっちで育てられる。だけん、出で行くのはあんたひとりたい!」と言われた私は“用済みの嫁”という烙印を押されリストラのように弾き飛ばされ泣く泣く独りぼっちで博多を去ったのだ。
「急にどうしたんだろう‥?」店を出てアパートに帰った僕は、放心状態でお金も受け取らず「今日は閉店‥」と言ったおばちゃんの様子が気になった。しかも、僕の名前を知ったとたんに‥。なんで‥?何かの占いか?―いや、ひょっとして僕を‥前から知ってた?
「私は、あなたの‥」この事実を伝えるべきか、黙っておくべきか‥。いろいろ逡巡した挙句に―このままでいい。このままがいい。あの子が店に来てくれさえすれば十分だ。そのためにはこのままじゃなくてはならない。と決心する。なぜなら‥事実は時に人を傷つけてしまう。―だから事実を伝えることがいつも正しいとは限らない―。昨日と変わらない今日を何事もなかったように過ごせることが今のあの子と私のためでもある。きっとそうだ。この事は誰にも告げることなく墓場まで持っていく覚悟を決めて仕込みのために店へと向かった。
その日はいつもより残業が延びてかなり遅い時間に仕事が終わった。もうとっくにあの店は閉まっているだろうと諦めてコンビニで適当に買い物を済ませてアパートに向かった。しかし、昨夜のことが頭から離れない。「あのおばちゃんは、いったい‥?」と思えば思うほど居ても立ってもいられなくなり踵を返して店へと駆け出して行った。――昨夜、父に電話した時に言われたことを確かめるために‥――。
店に着くとおばちゃんが外へ出て暖簾を畳みかけているところだった。「こ、こんばんは‥」「あらーっ、今帰って来たの?ずっと待っていたけど今日は来ないのかな?と思って閉めるとこだったけど、よかったら何か食べていく?」「いや、あの‥」「気にしないでいいのよ。どうせ暇だから、さあ入って入って」そう言っておばちゃんは嬉しそうに僕を店内に押し込んだ。
「残りものでいいでしょう?すぐ作るから待っててね。」「あの‥」「ん‥?どうしたの?あっ、何か食べたいリクエストでもある?」「いえ、あの‥」「‥お父さん、いや‥あの、父との電話で訊きました。おばちゃんと僕はどういう関係かって。ひょっとしたら、父はおばちゃんのこと知ってるんじゃないかって‥」「えっ‥⁈ あなたのお父さん‥何て言ったの?」「直接その人に聞いてみろって。そしたらわかるって。そして昔、父もこの街に住んでいて、この食堂の大将と仲良くなり当時のおばちゃんと知り合ったって‥。だから、僕がこの街で就職するのは反対だったと‥」
「そう‥」それを聞いてしばらくその場で俯いていたおばちゃんは、突然僕のそばに走り寄って膝から床に泣き崩れた。「ご、ごめんなさい、ごめんなさい。昨日、博多に住んでたって聞いて‥。年も同じだし。そして名前まで‥。これは人違いじゃない、確かに私の息子だってわかったの。本当に、本当にごめんなさい‥」それを見てあわてた僕はおばちゃんの両腕を掴んでテーブルの椅子にそっと座らせ、沸き上がる心の声をおばちゃんに届けた。
「僕は―。僕の本当のお母さんは僕を捨てて逃げたって、幼い頃から祖母や母に言われて育ってきました。すごく悲しかったです。でも、ずっと疑問でした。そんなことする母親が本当にいるのかな?って。それはたぶん―僕が本当の母親からそんなことされた、と思いたくなかった、からかも知れません。だけど、もし僕の本当のお母さんが僕にそうしたとしたら‥そこにはきっと何かがあった。そうせざるを得ない何かが‥」
「・・・・・・・・・」
「何も言わなくてもわかります。言えないことが答えになっているから。一緒に暮らしたいけどそれが出来なかった理由、それを言えないほど辛いことがあった。でも―昨日、僕を見てまるで“息子が目の前に座ってる”ようで嬉しいって‥言ってくれた言葉ではっきりとわかりました。どんなに離れていても僕をずっと思ってくれていたんだって」
「ごめんなさい。私、頭が混乱して‥何も、何も話せない。だからお願い。今日は、今日のところは‥もう帰ってほしい」
「いやだっ!もう‥逃げないでください。僕の目の前からいなくならないでください。僕だって‥。僕だって事実を知るのは怖かったし逃げたいとも思った。でも、会いに来たんです。やっぱり本当のことを知りたかったから。そして今、すごく嬉しいです。おばちゃんが僕の本当の“お母さん”だとわかってすごく嬉しい。だから会いたい時にいつでも会えるこの場所にずっといてください。誰かのせいで親子が離ればなれになるなんてもういやです。この奇跡のような再会を無駄にしたくない。いや、絶対に無駄にしちゃいけないです!僕は‥僕を産んでくれた人を“お母さん”って呼びたい。堂々と“お母さん”って呼びたい。だから今まで流してきた悲しくて辛い涙はもう流さなないでください。そして笑ってください。だって、おばちゃんは、僕の本当の“お母さん”なんだから‥。僕は“お母さん”の笑顔が見たいんです」
「あ、ありがとう‥。あのね、私は今、悲しくて泣いてるわけじゃないの。こんなに立派になったあなたを見て嬉しくて‥」そう言うと彼女は立ち上がり店の奥から封筒の束を持ち出し僕に手渡した。「これはね、あなたの誕生日に毎年書いた手紙よ。小学校や中学校の入学・卒業のお祝いに書いた手紙も入ってる。あなたに読んでほしくて書いたけど、郵送してもきっと捨てられるとわかっていたから“切手のない手紙”なんだけど、よかったら家で読んでくれる。それから‥お腹空いたでしょう?チャーハンでいい?」と言われた僕は思わず吸い込んだ息のせいで鼻の奥がツーンとして「はい」と言う返事が涙声になった。
やがてフライパンに投げ込んだ具材とご飯をお玉で混ぜ叩く乾いた音が静かな店内に響く。その間、ずっとカウンターの中を眺めていた僕の視線に気づいた彼女はにっこり笑ってこう言った。「あのね、いきなり“お母さん”なんて言われると照れ臭いから、今まで通りおばちゃんって呼んでくれる?その方が気が楽だもん。その代わりできるだけお店に来てちょうだい。それと‥これからはかしこまった言葉はお互いなしね」「はい。そうします、じゃなかった‥うん。そうする」「そう、それ。それでいい。はーい、チャーハンできたよ」
「う、うまい。あっ、そうか!僕、今、気づいたよ」「えっ、何を?」「僕はこの店で、“おふくろの味”を知らないうちに食べていたんだね。本当のおふくろの味、だからいつもおいしかったんだって」そう言うとおばちゃんの顔が再びぐしゃぐしゃになりかける。それを隠すようにおばちゃんは言った。「大げさなこと言わないで、早く食べてしまいなさい。明日も仕事早いんでしょ」「うんっ!」
家に帰って手紙を読んだ。読めば読むほど涙があふれて止まらない。僕の成長を綴ったアルバムにはおばちゃんの写真はない。でもアルバムのどの写真より思い出に残るこの手紙を書いてくれた僕の本当のお母さん。「ありがとう。僕を産んでくれて、僕の成長を遠くからずっと願ってくれて、そして再び出会ってくれて、本当にありがとう」―お母さん。―
この本を読んで「いいね!」と思った方は
下のボタンをクリックしてください。
下のボタンをクリックしてください。
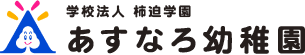
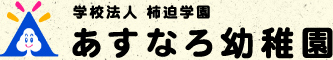


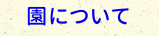
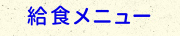
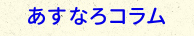
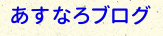
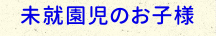
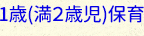
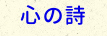
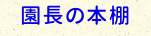


 閉じる
閉じる
 5
5